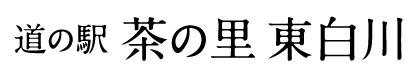東白川村の茶葉の歴史
東白川村の茶業の歴史は詳かではありません。
一説として村誌「東白川誌 通史編」には以下のように紹介されています。
※村誌「東白川誌 通史編」より許可を得て抜粋させていただきました。
茶業
その昔、大沢村番龍寺(蟠龍寺)の住職が山城国宇治から茶の実を持ち帰り、里人に与えて茶の栽培を奨めたのが始まり。

貞享元年(1684年)「神土村年貢通帳」には藩への御用茶を納めた記録があり、享保年間(1716~35年)以降にも毎年御用茶を納めるなど、この地方屈指の茶の産地であった。
往時の茶製法は「七度煎り」と称し、茶の生葉を強く熟した平釜(または鍋)で炒って、それを搓揉したのち、やや火力を低めた釜で再び炒り、またこれを搓揉する。
こうして漸次釜の温度を下げながら数回繰り返したのち、陰干しにした。並製はきわめて粗製で、一度湯を通して乾燥しただけであった。
幕末ごろには生茶の生産量も増えて、製法も釜製と称し、従来の七度炒りの手間数を簡略して一度釜で炒ったものを蓆(むしろ)の上で丹念に揉み、風乾(日陰乾)にするのが一般的となった。
この陰乾茶を「青製」または「青茶」といい、また日乾によって黒色に変したものを「黒茶」または「黒口」といい、これは品質が悪いとされた。しかし、この時代には在来からの自給的性格が強く、その品質においての商品性は余り問題にされなかったようである。
製茶法の改良

茶は、本村にとって生糸・繭につぐ重要特産物で、明治5~8年(1872~75年)にかけて海外市場への道が開かれたことによって、にわかにその商品性を高め、明治14年現在における茶の搬出高は神土村の840貫を最高に、五加村が620貫、越原村128貫を記録し、三か村合計価額は2379円およんだ。
茶の出荷販売状況
本村で生産された茶の出荷販売先は、信州および飛騨方面で、仲買人が各農家を回って買い集めた荒茶を精製して、各地の茶商へ輸送販売した。

明治12年(1879年)に各戸長役場で作製した「諸件目調書」によれば、当時県の製茶改会社から製茶売買鑑札を受けていた仲買人は、神土村27人、五加村16人で、その多くは自らも茶を生産し、また、繭や生糸の仲買も兼ねていた。
大正期に入ると、荒茶のほかに生葉を買い入れて直接加工する業者も現れた。五加では井戸省三・高告一郎・神土では安江安太郎らがそれであったが、中には村外から出張する業者も少なくなかった。
茶業の近代化
終戦から昭和28年ごろまでの村の産業統計の中には、茶の生産に関するものが除外されており、その間の生産量等は不明である。
昭和24年ごろ、農協事業として茶園改良と優良品種(ヤブキタ)の導入が始まり、茶の換金作物としてとしての有効性が認識されるようになった。そして昭和28、9年ごろには、村内各地で有志による茶業研究グループなどが誕生するようになり、長期にわたって不振を続けた茶業部門にもようやく増産への灯りが点った。
こうして、茶業振興への関心は次第に高まり、生産量も徐々に伸びたが、これは一気に、白川茶の一大生産地化へと本格的な動きに移ったのは、昭和35年に樹立された「新農村計画」以降のことであった。すなわち、この計画では、茶は、稲作・養蚕・畜産と並ぶ本村の基幹作目として、向こう5カ年間に50ヘクタールの集団茶園造成をはじめ緑茶共同加工施設の建設等の事業が盛り込まれた。

一方、茶の販売については、昭和38年から指定業者による競争入札となり、価格差などの問題が改善されて入札相場は常に高値を呼び白川茶の真価を高めている。
ことに品質向上については45年8月に行なわれた岐阜県茶業総合品評会において、本村からの出品茶8点が、農林大臣賞を獲得したほか、1等2点、2等3点、3等2点と出品茶全部が上位入賞の快挙を成し遂げ、郷土の特産「白川茶」の名声を高めるなど、ここに名実ともに白川茶主産地としての地位を不動のものにしたのである。
※この農林大臣賞は51年までの連続7回の記録を誇っており、関西茶品評会でも常に上位に入賞するなど、今や全国有数の銘柄茶に成長している。