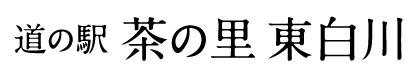東白川村の茶の起源は、その昔450余年前「蟠龍寺(ばんりゅうじ)」の住職が山城国宇治から茶の実を持ち帰り、里人に与えて茶の栽培を奨めたのが始まりと伝えられています。

それが地味に適し、「深山幽谷ニシテ朝夕川霧多ク、空気ハ常ニ湿気ヲ含ミ、表土能ク乾燥スル」ところとして、良質な茶葉を産し、白川流域を中心に近郷に広まったといいます。

今も残る蟠龍寺の寺跡の石垣。
そこには、今もなお参道脇の石垣に自生する在来種が里人の手によって守り受け継がれています。
弊社、新世紀工房ではこの度のホームページ制作で茶の文化をあらためて見つめなおしたところ、私達は「大切なことを忘れている」と気付きました。それは先人の血と汗の結晶の上に商いをさせていただいていることへの感謝です。
今は地主の皆様やかつての檀家の皆様が、この地を荒らさず守ってくださいますが、茶業関係者のみんなの手で守り受け継がなければならないことだと思い、今私たちにできることは何かと考えた結果、皆様のご助力を得てこの度の「蟠龍寺大門茶の献茶祭」を執り行うことができる運びとなりました。
蟠龍寺大門茶(ばんりゅうじだいもんちゃ)を摘む

参道の石垣に自生する在来種を丁寧に摘みます。
この在来種は、やぶきた等と比較して茶葉自体が大きくわずかに黄色がかっている葉を持っています。
まさに石垣が守ってくれていた、東白川茶の起源の茶葉を摘んでいます。
大門茶を揉む

摘んだ茶葉はすぐに蒸しの工程へ持ち込みます。
蒸す時間は数十秒程度。茶葉の状態はもちろん気温や湿度などから経験に基づいた時間蒸されます。

生の茶葉の香りの違いが仕上がりにどう影響するのか。この茶葉を真に蘇らせる最大限の努力をしたい。

粗揉機で採れたての茶を揉みます。
数分後ごとに、取り出して揉み具合をチェックします。

昭和初期から使い込まれている製造機。
お茶を製造する各工程は、昔ながらの手揉みを再現する装置を使って時間をかけながら行います。
ほとんどすべての工程に熱が使われますが、それは人肌かそれより少し上の温度で行われます。

精揉機にかけると、いよいよ皆さんご存知のお茶の葉らしくなってきます。

荒茶として仕上がった「蟠龍寺 大門茶」。
茶葉自体が大きく、とても深い緑をしています。
その香りはやさしくて、どこか懐かしさを感じることができます。
献茶祭
この荒茶を新世紀工房へ持ち帰って再火して袋詰めし、450年の時を偲ばせる「大門茶」が完成しました。
この大門の新茶を12代の住職様に献上して感謝報告するとともに、東白川村の茶業の繁栄を祈念する「献茶祭」を地元の皆様の協力を得て開催いたしました。

茶を広めたと伝えられる11代の住職が眠る、東白川茶発祥の地「蟠龍寺」の寺跡。

大門の新茶を12代の住職様に献茶し感謝報告するとともに、東白川村の茶業の繁栄を祈念して、深く深くお祈りさせていただきました。

献茶された「蟠龍寺大門茶」
このお茶をいつか多くの人に味わっていただけたらと切に願います。